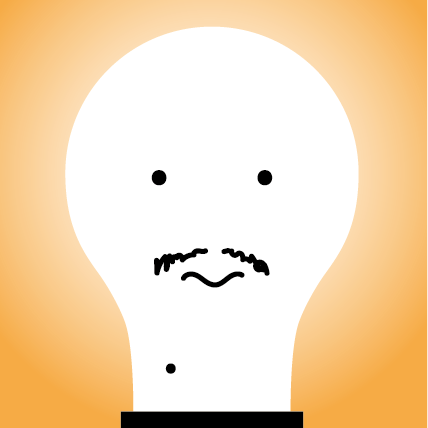第15回「ドラマー ②」
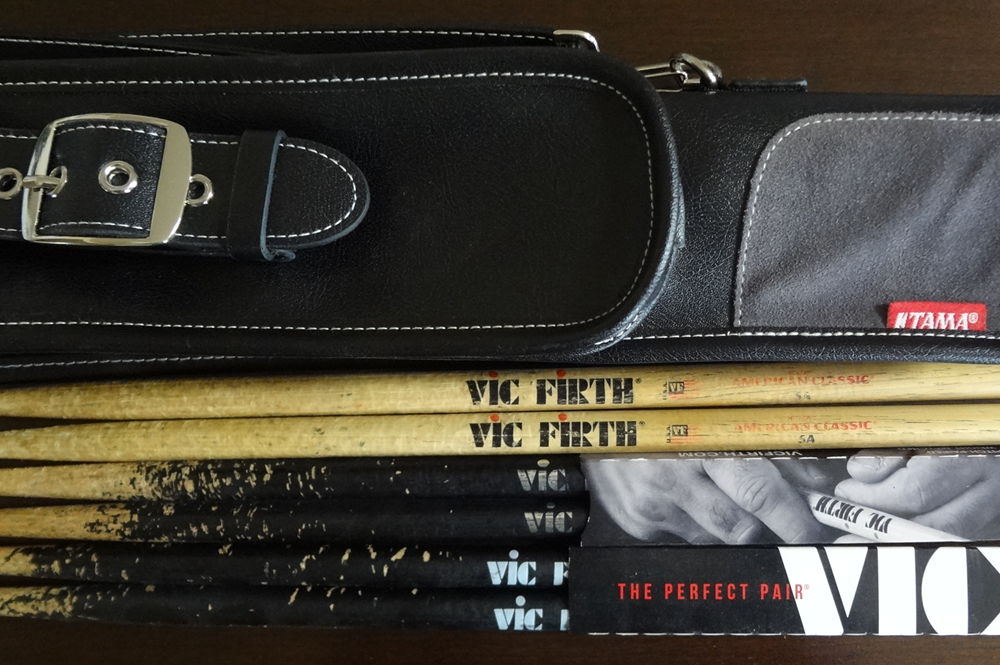
皆さん、こんにちは。「くのいち」ことクノテツヤです。
さて、今回は、以前お送りしたドラマー特集の第二弾ということで、前回紹介しきれなかった僕の大好きなドラマー達を取り上げて、彼らの演奏を聴くことが出来るお気に入りの曲をお届けしたいと思います。
―1曲目―
「シンプル・イズ・ベスト」とは、この人のためにあるような言葉です。
ムダを削ぎ落としたシンプルなドラミングが、しなる鋼(はがね)のように粘りのある強靭なビートを生み出し、バンドを突き動かしていく、その姿には感動すら覚えます。聴いてください。
♪ AC/DC「バック・イン・ブラック」 <ドラム:フィル・ラッド>
“Back In Black” by AC/DC <Drums: Phil Rudd>
この曲は、AC/DCが1980年に発表した歴史的名盤「バック・イン・ブラック」のタイトル・トラックで、彼らの代表曲であると同時に、HR/HMの歴史に残る名曲です。
ミディアム・テンポのシンプルなドラムを聴いて、うっかり「これなら自分にも叩けそう」なんて思ったら大間違い。音符をなぞるだけなら、たしかに難しくないけれども、シンプルであるがゆえに誤魔化しようのないむき出しのビート、そしてテクニックだけでは決して生み出せないあの強力なグルーヴは、ちょっとやそっとじゃ真似できません。憧れます。
一時期、フィル・ラッドはAC/DCを離れたりもしましたが、やっぱりAC/DCには、どんなに上手いドラマーよりもフィル・ラッドがしっくりきます。これが、バンドの面白くも不思議なところです。
―2曲目―
この人は、際立って個性的なドラマーというわけではないのですが、パワフルで胸のすくようなドラミングを聴かせてくれる、僕の大好きなドラマーです。聴いてください。
♪ エース・フレーリー「リップ・イット・アウト」 <ドラム:アントン・フィグ>
“Rip It Out” by Ace Frehley <Drums: Anton Fig>
この曲は、キッスのオリジナル・ギタリスト エース・フレーリーが1978年に発表したソロ・アルバム「エース・フレーリー」の冒頭を飾る、ストレートで痛快なハード・ロック・ナンバーです。
このアルバムで初めて耳にしたアントン・フィグのエネルギッシュで豪快なドラミングは、思い切り僕のツボにはまりました。
その後、エースはキッスを脱退してソロ活動を始めますが、そのとき結成したフレーリーズ・コメットというバンドのドラマーがアントン・フィグだと知ったときは大喜びでした。
嬉しいことに、エースのソロ活動にはずっとアントン・フィグが関わっており、昨年リリースされたエースの最新アルバム「10,000 VOLTS」でも、彼のドラム・プレイを聴くことが出来ます。
そんなアントン・フィグが、実はキッスの影武者ドラマーとして、「地獄からの脱出(原題:Dynasty)」「仮面の正体(原題:Unmasked)」でドラムを叩いていたことを、かなり後になってから知りました。レコードにはクレジットもないので、僕は、ピーター・クリスのプレイ・スタイルが「地獄からの脱出」で突然変わって、ツー・バスまで使い始めた……と何の疑いもなく思い込んでいました。
実は、これらのアルバムでピーター・クリスはドラムを叩いていない(自作曲の「ダーティ・リヴィン」のみ参加)、という事実を知ったときはショックでした。でも、そのお陰で、豹変したプレイ・スタイルの謎が解けてスッキリしたのと同時に、アントン・フィグは豪快なだけでなく、細かいセンスが光る実力派の職人ドラマーだということが分かり、ますますファンになりました。
―3曲目―
同じ1980年に発表された僕の大好きなアルバム2枚に、ある共通のドラマーが参加していました。特にツー・バスを駆使した超絶プレイに、「この凄いドラマーは、一体どういう人なんだろう?」と気になって仕方がありませんでした。聴いてください。
♪ ジェフ・ベック「スペース・ブギ」 <ドラム:サイモン・フィリップス>
“Space Boogie” by Jeff Beck <Drums: Simon Phillips>
この曲は、ジェフ・ベックが1980年に発表した3作目のソロ・アルバム「ゼア・アンド・バック」に収録されている、タイトル通り宇宙空間を駆け抜けていくような、スピード感あふれるシャッフル・ナンバーです。
このアルバムでドラムを叩いているサイモン・フィリップスは、同じ1980年に発表されたマイケル・シェンカー・グループのデビュー・アルバム「神(帰ってきたフライング・アロウ)(原題:Michael Schenker Group)」でもドラムを叩いていて、「すごいドラマーだなぁ」と、強烈な印象を受けました。
ドラム・プレイはもちろんのこと、サイモン・フィリップスが操るツー・バスの巨大セットが、十代の頃の僕にはたまらなく魅力的でした。また、一般的なドラマーとは違った彼の演奏方法にも興味津々で、初めてオープン・ハンド奏法(両手を交差させないでドラム・セットを叩く演奏形態)というものを知りました。
僕にとっては、フュージョンやHR/HM系の印象が強いサイモン・フィリップスですが、それ以外にも、ルーツであるジャズに始まり、AOR、プログレッシヴ・ロック、ポップス……と、ジャンルの垣根を超えて大活躍しているスーパー・ドラマーです。
―4曲目―
この人の登場は、ドラマーに対する典型的なイメージ、後ろの方で目立つことなく「縁の下の力持ち」としてバンドを支える……そんな従来のドラマー像を思い切りひっくり返してくれました。ドラマーも、バンドの中で一番カッコ良くて目立つ存在になれることを身をもって証明した、憧れの存在です。聴いてください。
♪ モトリー・クルー「ワイルド・サイド」 <ドラム:トミー・リー>
“Wild Side” by Motley Crue <Drums: Tommy Lee>
この曲は、モトリー・クルーが1987年に発表した4作目のアルバム「ガールズ・ガールズ・ガールズ」のオープニングを飾る彼らの代表曲です。
トミー・リー最大の魅力は、自らのことを「Low IQ, High Energy」と称して、常識外れのパフォーマンスで常に皆をアッと驚かせる、その徹底したエンターテインメント精神にあり、プロアマ問わず多くのドラマーにとてつもなく大きな影響を与えました。僕自身も、ドラムを叩きながらスティックをぐるぐる回すトミー・リーの姿に憧れて、何度もスティックをすっ飛ばしながら、スティック回しの練習をしました。
ところが、当のトミー・リー本人は、スティックを回すだけでは飽き足らず、とうとう自分自身をドラムセットごと回してしまいました……。この「ワイルド・サイド」のPVでは、その度肝を抜くトミー・リーの360度回転ドラムを拝むことが出来ます。見たことのない方は、ぜひ一度。
―5曲目―
ドラマーの基本的な役割は、安定したリズム・キープによる演奏の土台作りにあります。
ところが、なかには、正確なタイム感とかテクニックといった、上手い下手で語られるような次元を超越して、ほとばしる音楽への愛情と情熱だけで、すべてをねじ伏せてしまう強者(つわもの)がいるのです。聴いてください。
♪ メタリカ「サッド・バット・トゥルー」 <ドラム:ラーズ・ウルリッヒ>
“Sad But True” by Metallica <Drums: Lars Ulrich>
この曲は、メタリカが1991年に発表した5作目のアルバム「メタリカ」(通称:ブラック・アルバム)に収録されています。個人的にはラーズ史上最高のグルーヴを聴くことが出来る曲だと思っています。
このアルバムは、スラッシュ・メタルと呼ばれていた頃の高速ビートや、前作「メタル・ジャスティス(原題:…And Justice For All)」で顕著だったプログレ的展開はすっかり影を潜めていて、たしかに一抹の寂しさはあったのですが、ここで聴くことの出来る強力なグルーヴと充実した楽曲群の前では、そんなことは取るに足らないことだと思ってしまう、そんな圧倒的な完成度を誇っていました。
ところで、僕の大好きなこの「サッド・バット・トゥルー」という曲に関して、ひとつだけ、どうしても忘れられない残念なことがありました。
この曲の一番の快感ポイントである、サビの歌詞 “sad but true” の前に出てくる「ガッ・ガッ・ガッ」という二拍三連のフレーズが、なぜかライヴでは単純な三拍で演奏されていて、あまりのしまりのなさに、思い切りずっこけてしまいました。
ここは絶対に変えちゃいけないところでしょ……と思っているのは、僕だけ?
最近のライヴではどうなっているのだろう?
―6曲目―
この人は、超絶プレイも難なくこなすテクニックを持ちながらも、決して歌の邪魔をせず、いつも曲の魅力を最大限に引き出すことを最優先としたドラミングを聴かせてくれます。そんな彼が、曲の求めに応じて、いざ本領を発揮したらどれだけ凄いことになるか……聴いてください。
♪ MR. BIG「コロラド・ブルドッグ」 <ドラム:パット・トーピー>
“Colorado Bulldog” by MR. BIG <Drums: Pat Torpey>
この曲は、MR. BIGが1993年に発表した3作目のアルバム「バンプ・アヘッド」の冒頭を飾る、彼らお得意のスピード・チューンです。いつ、何度聴いても、このスリリングな演奏にはしびれます。
MR. BIGというバンドの基本コンセプトは、ブルースやソウルに根差したいい曲、いい歌をちゃんと聴かせることにあるため、パット・トーピーは、いたずらにテクニックをひけらかすような演奏は決してしません。そうかと思えば、一見何でもなさそうな普通の曲で、とんでもなく難しいことをサラッとやってのけ、しかも曲の一部として自然に聴かせてしまうのが、何とも憎いところです。
例えば、最初はただのメロディアスでおとなしい曲だと思っていた「テイク・カヴァー」ですが、リズム&ドラムス・マガジンで、この曲はリニア・パターン(楽譜上では、音符が縦に重ならず、1直線(リニア=Linear)につながるドラム・パターン)による高難度の曲だということを知って、早速、練習してみました。たしかに無茶苦茶難しいです。それでも、何とかパターンは叩けるようになったけれど、まだまだ原曲のテンポでは演奏が続きません……。
パット・トーピーの凄さにあらためて脱帽です。
―7曲目―
このドラマーは、もともと超売れっ子の一流スタジオ・ミュージシャンで、テクニック的に優れているのはもちろんのこと、曲を引き立たせる抜群のセンスとロック魂を感じさせる熱いプレイが魅力的です。聴いてください。
♪ TOTO「子供の凱歌」 <ドラム:ジェフ・ポーカロ>
“Child’s Anthem” by TOTO <Drums: Jeff Porcaro>
この曲は、TOTOが1978年に発表した記念すべきデビュー・アルバム「宇宙の騎士(原題:Toto)」のオープニングを飾る、TOTOの真骨頂とも言える、プログレ要素とキャッチーさを兼ね備えた、劇的なインストゥルメンタル・ナンバーです。
いきなり頭拍抜きのトリッキーなフレーズで曲が始まり、当時は「これ、一体どうなっているの?」と、多くのドラマーの頭を悩ませたといいます。僕自身は、結局、自力では叩き方を解明することが出来ず、ドラム教室でこのフレーズのからくりを教わりました。
この曲を叩けるようになったとき、メチャクチャ嬉しかったのを覚えています。
ところで、ジェフ・ポーカロと言えば、彼の代名詞となった「ロザーナ」におけるハーフタイム・シャッフルが有名です。これがまたとんでもなく難しいのですが、いつかこの曲をちゃんと叩けるようになりたいと思っています。
―8曲目―
このドラマーにハマったのは、ある曲の印象的なドラム・パターンがきっかけでした。聴いてください。
♪ ジャーニー「ドント・ストップ・ビリーヴィン」 <ドラム:スティーヴ・スミス>
“Don’t Stop Believin'” by Journey <Drums: Steve Smith>
この曲は、ジャーニーが1981年に発表した傑作アルバム「エスケイプ」のオープニングを飾る永遠の名曲です。
この曲を印象付けるドラム・パターンの魅力は、曲が進むにつれて少しずつフレーズが発展していくドラマチックな展開・構成、そして、シンバルのカップ音のキラキラと輝くような響きとタムが織りなす、魔法のように美しいコンビネーションです。
僕はこの曲を叩けるようになりたくて、音楽教室の発表会の希望演奏曲として「ドント・ストップ・ビリーヴィン」を挙げて、ラッキーなことに無事採用されました。
この曲は、一般的なクロス・ハンド奏法(腕を交差させてドラム・セットを叩く演奏方法:右利きの場合は、右手でハイハット、左手でスネアを叩く)ではなく、腕を交差させずに、左手でハイハット、右手でスネア(およびタム、シンバル)を叩くという、サイモン・フィリップスのところでも出てきた「オープン・ハンド奏法」を使っていることが判明。猛練習の結果、この曲を叩けるようになったときの喜びはひとしおでした。
―9曲目―
この人は、マシンのように正確なリズムを刻み、どんな細かいフレーズでも粒立ちのハッキリした綺麗な音を鳴らし、それでいてグルーヴ感のある気持ちいいドラミングを聴かせる、僕の大好きなドラマーです。聴いてください。
♪ 吉井和哉「黄金バッド」 <ドラム:ジョシュ・フリーズ>
“Golden Bad” by Kazuya Yoshii <Drums: Josh Freese>
この曲は、吉井和哉さんが2006年に発表したソロ3作目のアルバム「39108」に収録されている、スピード感あふれるロック・ナンバーです。当時、「こういうのを聴きたかったんだよね」と久々に思わせてくれた、大好きな曲です。
吉井さんのソロ活動時代の盟友とも言えるジョシュ・フリーズですが、彼が2009年に発表したソロ・アルバム「Since 1972」を聴いたとき、そこに吉井さんのソロ・アルバムに通じる独特の空気感を感じ、とても驚きました。そして、なぜ吉井さんとジョシュ・フリーズが、あんなにもウマが合ったのか、その理由が分かったような気がしたのでした。
ジョシュ・フリーズは、アヴリル・ラヴィーン、ディーヴォ、ナイン・インチ・ネイルズ、スティング……と、数多くの名だたるバンド/ミュージシャンから引っ張りだこの超売れっ子ドラマーです。
最近では、フー・ファイターズに参加したと聞いて、楽しみにしていたのですが……どうやら解雇されてしまったようです。残念。
―10曲目―
この人みたいに、どれだけ叩きまくっても、まったくうるさく感じさせない、そして歌のジャマもしない、そんなドラムを叩けるようになりたいと常々思っている、僕の大好きな日本人ドラマーです。聴いてください。
♪ ザ・クロマニヨンズ「ギリギリガガンガン」 <ドラム:KATSUJI (桐田勝治)>
“Giri-Giri-Ga-Gan-Gan” by The Cro-Magnons <Drums: KATSUJI (Katsuji Kirita) >
この曲は、2007年にリリースされたザ・クロマニヨンズ3枚目のシングルで、現在もライヴに欠かせない鉄板曲として、絶大な人気を誇っています。ちなみに、この曲は「ワルボロ」という映画の主題歌でもありました。原作の小説「ワルボロ」をマーシーが推薦していたという話を聞き、すぐに本を買って読みました。もちろん、映画も劇場で観てきました。
ところで、この曲におけるKATSUJIさん、何とBPM=208という高速テンポにも関わらず、ハイハットを8分で刻み続けるという驚異的なことをやっています。動画を何度もチェックして、手首のアップ&ダウンや、8の字を描くような腕全体の大きくしなやかな動きをマスターしようと、かなり練習をしたのですが、いまだに原曲のテンポでは、とてもじゃないけど安定した演奏が出来ません……。
しかし、残念がってばかりいても出来るようにはならないので、引き続き練習あるのみです。
頑張れ、俺。
* * *
まだまだ紹介しきれていない好きなドラマーが沢山いるので、もしかしたら、性懲りもなく第三弾をお送りするかもしれません。お楽しみに?
-今回も最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。
それでは、またお会いしましょう。See Ya!
ー第15回「ドラマー ②」プレイリストー
| No. | 曲名 Song Title | アーティスト Artist |
|---|---|---|
| 1 | バック・イン・ブラック Back In Black | AC/DC AC/DC |
| 2 | リップ・イット・アウト Rip It Out | エース・フレーリー Ace Frehley |
| 3 | スペース・ブギ Space Boogie | ジェフ・ベック Jeff Beck |
| 4 | ワイルド・サイド Wild Side | モトリー・クルー Motley Crue |
| 5 | サッド・バット・トゥルー Sad But True | メタリカ Metallica |
| 6 | コロラド・ブルドッグ Colorado Bulldog | MR.BIG Mr. Big |
| 7 | 子供の凱歌 Child’s Anthem | TOTO Toto |
| 8 | ドント・ストップ・ビリーヴィン Don’t Stop Believin’ | ジャーニー Journey |
| 9 | 黄金バッド Golden Bad | 吉井和哉 Kazuya Yoshii |
| 10 | ギリギリガガンガン Giri-Giri-Ga-Gan-Gan | ザ・クロマニヨンズ The Cro-Magnons |
■■